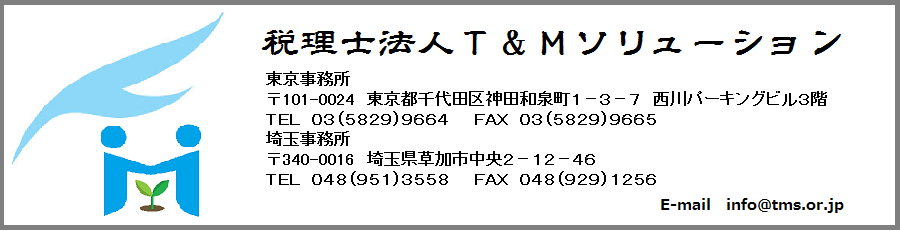
URL http://www.tms.or.jp
事務所だより 令和7年9月号
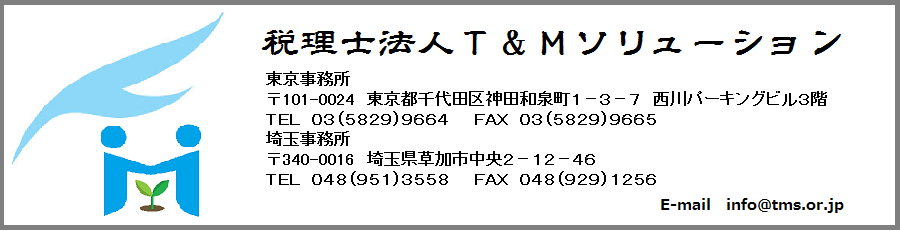
現在、新設法人が口座を開設したいと申し出ても、実店舗を持つ金融機関では、
まず断られます。
金融機関の業務が以前と異なってきていますが、今後、送金業 務も金融機関ではなくなるかもしれません。
最近、日本企業のJPYCが送金サービ スをする「資金移動業」の登録業者として国から認可され、今秋にも国内で初め て法定通貨に価値が連動する円建て暗号資産を発行して、それを売り買いするこ とで実質送金を可能とする見通しです。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2025年9月の税務
◆被相続人の家屋が未登記の場合 −相続空き家の特例−
◆中小企業白書を読み解く 雇用維持のための対策を
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆2025年9月の税務
-----------------------------------------------------------------------
9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆被相続人の家屋が未登記の場合 −相続空き家の特例−
-----------------------------------------------------------------------
◆空き家の特例は旧耐震の建物解消が目的
相続空き家の特例は、相続等で取得した被相続人居住用家屋及び被相続人居住 用家屋の敷地等を売却した場合、一定の要件を満たすときは、譲渡所得金額から 3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)までを控除できる制度で す。
この特例は、昭和56年5月31日以前に建築された「旧耐震基準」の建物の約半 数は耐震性がないものと推計されることから生活環境の悪化を防ぐため、相続人 の売却の際、譲渡所得に課税上の優遇措置を設けて空き家の解消を図ろうとする ものです。
したがって、この特例を利用しようとする相続人は、被相続人の居住用家屋が 「旧耐震基準」の時期に建築されていたことを証明しなければなりません。
しか し、その居住用家屋が未登記であった場合には登記事項証明書が存在しないため 、代替的な書類の取得が必要になります。
◆未登記の被相続人居住用家屋の代替書類
未登記の建物に相続空き家の特例の適用を受けようとする場合、確定申告書に 添付する書類は、譲渡所得金額の計算明細書に加え、次の書類で代替させます。
<要件1.被相続人から相続等によって取得したものであること>
遺産分割協議書の記載内容から被相続人の建物を取得したことが確認できます 。
<要件2.昭和56年5月31日以前に建築されたこと>
建物の建築確認済証、検査済証、建築請負契約書で建築年月を確認できます。
<要件3.区分所有建物登記がされている建物でないこと>
固定資産税の課税明細書、評価証明書、固定資産課税台帳に区分所有建物の記 載がないことで確認できます。
◆「被相続人居住用家屋等確認書」の添付
この他、相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこ とを証明するため、建物が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書 」の交付を受け、申告書に添付する必要があります。
未登記の建物であっても被相続人がそこで暮らしていたことを証明しなければ なりません。
建物を除却する場合も登記のある建物と同様、除却工事の請負契約 書、取壊し後、更地の日付入り写真を提出します。
意外に準備に苦労するのが電 気・ガス等の使用中止日を確認できる書類です。早めに対応して漏れがないよう にしましょう。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆中小企業白書を読み解く 雇用維持のための対策を
-----------------------------------------------------------------------
◆共通課題としての人材確保
2025年版中小企業白書によると、全国17,848者の中小企業・小規模事業者を対 象とした帝国データバンクの調査において、「人材確保」が最重要課題として挙 げられた割合が最も高い結果となりました。
中規模企業では「省力化・生産性向 上」、小規模事業者では「事業承継」がそれに続きますが、いずれにせよ人材の 確保・活用が経営基盤の安定に直結することは明白です。>
業種・企業規模を問わ ず、雇用を取り巻く環境が厳しさを増している現状が浮き彫りとなりました。
◆従業員不足の構造的背景
同白書では、従業員数の「過不足率」に関する景況調査も示されており、特に 中規模企業で人材の「不足感」が強く、建設業においてはその傾向が顕著です。
これは一過性の現象ではなく、労働人口の減少や業種ごとの働き手確保の難しさ など、構造的な課題が背景にあると分析されます。
このような中で、採用戦略の 見直しや職場環境の改善を通じて、いかに「選ばれる企業」になるかが問われて います。
◆実務で意識すべきポイント
人材不足への対応としては、単に採用枠を増やすのではなく、定着率向上に向 けた工夫が求められます。
例えば、短時間勤務制度やリモートワーク制度の導入による柔軟な働き方の提 供、資格取得支援などキャリア形成への投資、職場内コミュニケーションの活性 化などが挙げられます。
加えて、DXや省力化設備の導入を通じて限られた人材で 最大限の生産性を確保する施策も有効です。助成金制度の活用や、社会保険労務 士との連携による就業規則の整備も併せて検討したいところです。
◆次世代に向けた布石を
少子化が進む現代において人材の確保は今後ますます難易度が増すと予想され ます。
事業承継と絡めた「次世代人材」の育成、外国人材や高齢者の戦力化、業 務の見直しによる人手依存からの脱却など、中長期的視点を持った戦略が必要で す。労働市場の変化を的確に捉え、外部支援を活用しながら、自社に適した雇用 維持・拡大施策を構築することが、これからの中小企業経営における生存戦略の 鍵となります。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-金融機関の業務が以前と異なってきていますが、今後、送金業 務も金融機関ではなくなるかもしれません。
最近、日本企業のJPYCが送金サービ スをする「資金移動業」の登録業者として国から認可され、今秋にも国内で初め て法定通貨に価値が連動する円建て暗号資産を発行して、それを売り買いするこ とで実質送金を可能とする見通しです。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2025年9月の税務
◆被相続人の家屋が未登記の場合 −相続空き家の特例−
◆中小企業白書を読み解く 雇用維持のための対策を
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆2025年9月の税務
-----------------------------------------------------------------------
9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆被相続人の家屋が未登記の場合 −相続空き家の特例−
-----------------------------------------------------------------------
◆空き家の特例は旧耐震の建物解消が目的
相続空き家の特例は、相続等で取得した被相続人居住用家屋及び被相続人居住 用家屋の敷地等を売却した場合、一定の要件を満たすときは、譲渡所得金額から 3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)までを控除できる制度で す。
この特例は、昭和56年5月31日以前に建築された「旧耐震基準」の建物の約半 数は耐震性がないものと推計されることから生活環境の悪化を防ぐため、相続人 の売却の際、譲渡所得に課税上の優遇措置を設けて空き家の解消を図ろうとする ものです。
したがって、この特例を利用しようとする相続人は、被相続人の居住用家屋が 「旧耐震基準」の時期に建築されていたことを証明しなければなりません。
しか し、その居住用家屋が未登記であった場合には登記事項証明書が存在しないため 、代替的な書類の取得が必要になります。
◆未登記の被相続人居住用家屋の代替書類
未登記の建物に相続空き家の特例の適用を受けようとする場合、確定申告書に 添付する書類は、譲渡所得金額の計算明細書に加え、次の書類で代替させます。
<要件1.被相続人から相続等によって取得したものであること>
遺産分割協議書の記載内容から被相続人の建物を取得したことが確認できます 。
<要件2.昭和56年5月31日以前に建築されたこと>
建物の建築確認済証、検査済証、建築請負契約書で建築年月を確認できます。
<要件3.区分所有建物登記がされている建物でないこと>
固定資産税の課税明細書、評価証明書、固定資産課税台帳に区分所有建物の記 載がないことで確認できます。
◆「被相続人居住用家屋等確認書」の添付
この他、相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこ とを証明するため、建物が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書 」の交付を受け、申告書に添付する必要があります。
未登記の建物であっても被相続人がそこで暮らしていたことを証明しなければ なりません。
建物を除却する場合も登記のある建物と同様、除却工事の請負契約 書、取壊し後、更地の日付入り写真を提出します。
意外に準備に苦労するのが電 気・ガス等の使用中止日を確認できる書類です。早めに対応して漏れがないよう にしましょう。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆中小企業白書を読み解く 雇用維持のための対策を
-----------------------------------------------------------------------
◆共通課題としての人材確保
2025年版中小企業白書によると、全国17,848者の中小企業・小規模事業者を対 象とした帝国データバンクの調査において、「人材確保」が最重要課題として挙 げられた割合が最も高い結果となりました。
中規模企業では「省力化・生産性向 上」、小規模事業者では「事業承継」がそれに続きますが、いずれにせよ人材の 確保・活用が経営基盤の安定に直結することは明白です。>
業種・企業規模を問わ ず、雇用を取り巻く環境が厳しさを増している現状が浮き彫りとなりました。
◆従業員不足の構造的背景
同白書では、従業員数の「過不足率」に関する景況調査も示されており、特に 中規模企業で人材の「不足感」が強く、建設業においてはその傾向が顕著です。
これは一過性の現象ではなく、労働人口の減少や業種ごとの働き手確保の難しさ など、構造的な課題が背景にあると分析されます。
このような中で、採用戦略の 見直しや職場環境の改善を通じて、いかに「選ばれる企業」になるかが問われて います。
◆実務で意識すべきポイント
人材不足への対応としては、単に採用枠を増やすのではなく、定着率向上に向 けた工夫が求められます。
例えば、短時間勤務制度やリモートワーク制度の導入による柔軟な働き方の提 供、資格取得支援などキャリア形成への投資、職場内コミュニケーションの活性 化などが挙げられます。
加えて、DXや省力化設備の導入を通じて限られた人材で 最大限の生産性を確保する施策も有効です。助成金制度の活用や、社会保険労務 士との連携による就業規則の整備も併せて検討したいところです。
◆次世代に向けた布石を
少子化が進む現代において人材の確保は今後ますます難易度が増すと予想され ます。
事業承継と絡めた「次世代人材」の育成、外国人材や高齢者の戦力化、業 務の見直しによる人手依存からの脱却など、中長期的視点を持った戦略が必要で す。労働市場の変化を的確に捉え、外部支援を活用しながら、自社に適した雇用 維持・拡大施策を構築することが、これからの中小企業経営における生存戦略の 鍵となります。