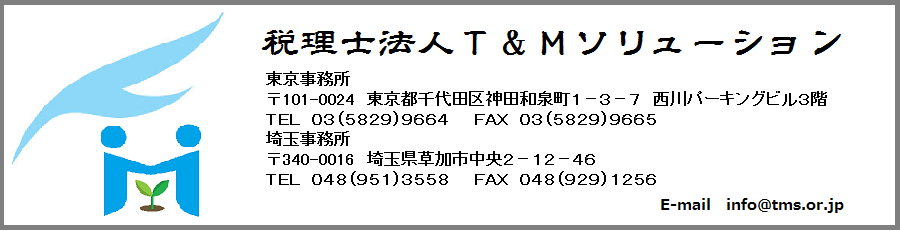
URL http://www.tms.or.jp
事務所だより 令和7年7月号
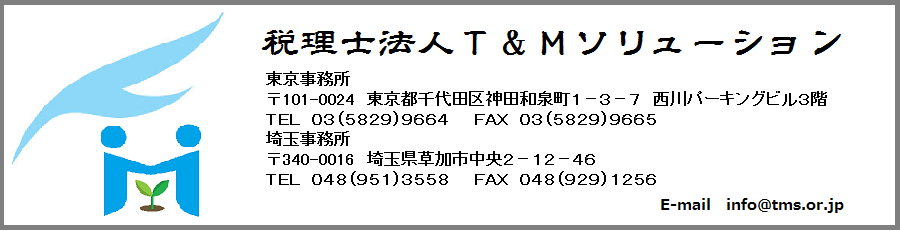
今年から19歳以上23歳未満の人(大学生のアルバイトを想定)について、特定扶
養控除の要件の見直しと特定親族特別控除の創設が行われ、所得税法上、給与収
入150万円までは、その親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受け
られるようになります。
これに伴い、健康保険の認定対象者(被保険者の配偶者 を除く。)が19歳以上23歳未満である場合には扶養要件を年間収入150万円未満 することとなりました。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2025年7月の税務
◆ホスピスで高齢者が亡くなった場合の小規模宅地等の特例
◆資本金等の額減少で均等割節税
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆2025年7月の税務
-----------------------------------------------------------------------
7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1 月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
7月31日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定 める日)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆ホスピスで高齢者が亡くなった場合の小規模宅地等の特例
-----------------------------------------------------------------------
◆ホスピスとは
日本ホスピス緩和ケア協会の案内によると、ホスピスとは、がんなど難病で治 療が困難となった患者さんとその家族のために医師・看護スタッフがチームで緩 和ケアを実施する施設です。
1960年代にイギリスで発祥し、これまで医療が担っ てきた「検査・診断・治療・延命」ではなく、終末期医療の患者さんの痛みと不 安を和らげ、患者さんに寄り添い、本人と家族のQOL(クオリティ・オブ・ライ フ)向上を目的としています。
緩和ケアは在宅で受けることも可能ですが、高齢者の場合、近年は子供世帯の 負担の大きさから病院内の緩和ケア病棟や地域で医師と連携できる有料老人ホー ムなどがホスピスとして利用されています。
◆小規模宅地等の特例適用は条文等から判断
高齢者の方がホスピスで亡くなった場合、小規模宅地等の特例(特定居住用宅 地)の適用関係について、税法にはホスピスという用語は出てこないので、国税 庁の質疑応答事例や条文などから判断します。
病院で亡くなった場合、質疑応答事例では、病院の機能等から居宅で起居しな いのは一時的なものであり、入院後、居宅が他の用途に供されたような特段の事 情がない限り、生活の拠点は居宅にあり、小規模宅地等の特例の適用対象になる としています。
したがって緩和ケアで病院に入院していた場合も同様の扱いとな るものと思われます。
次に、有料老人ホームで緩和ケアを受けていた場合は、租税特別措置法第40条 の2第2項の要件に該当するかを確認します。
すなわち、被相続人が相続開始直 前において
(1)要介護または要支援状態にあること、かつ、
(2)老人福祉法第29条 第1項に定める施設であること、
そのうえで自宅の生活資材はそのまま、賃貸や 事業の用に供していないなどの要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用対象 になります。
また、特別養護老人ホームなど他の施設の場合でも、各法令で定め る施設に該当すれば、同様に小規模宅地等の特例の適用対象になります。
◆有料老人ホームの確認方法
有料老人ホームの事業者は、事業所の設置に際し、事前に都道府県知事に届出 が義務付けられ、公開されています。
また、契約に際して交付される重要事項説 明書の記載をもとに事業内容を確認することもできます。小規模宅地等の特例適 用について判断する際は、上記(1)(2)の要件を満たしているかをしっかり確認し ましょう。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆資本金等の額減少で均等割節税
-----------------------------------------------------------------------
◆法人住民税の均等割
法人道府県民税の均等割税は資本金等の額の5区分、法人市町村民税の均等割 税は資本金等の額の5区分と従業員の数の2区分とによって決められています。
所得の有無に関係なく、赤字でも負担しなければなりません。資本金等の額1000 万円以下、従業員数50人以下の分類区分が税負担の最少区分です。
◆減資で均等割節税への試み
ところで、この税負担の軽減を企図して資本金の減少手続きをする場合があり ます。
でも、資本金を減らしただけでは均等割税の軽減はできません。減資資本 金は資本剰余金の額に振り替わるだけで、資本金等の額の総額に影響しないから です。
資本金等の額は税法上の概念で、株式発行や組織再編で受け入れた出資額の内 、資本金とした金額とそれ以外の金額の合計とされており、会計上の「資本金+ 資本剰余金」に近い概念です。
◆資本金等の額の減少への税の抵抗
なお、資本金等の額を実際に減らそうとして有償減資や資本剰余金の配当をし たとしても、資本金等の額が直ちに減少するとは限りません。
税務的には、「資 本金等の額×資本剰余金減少額÷簿価純資産額=減少資本金等の額」の算式で計 算されることになっているからで、簿価純資産の中に利益剰余金がある限り資本 剰余金の減少を直ちに資本金等の額の減少にすることはできません。
例えば、資本金2000万円、資本剰余金0円 利益剰余金1000万円の会社が資本 金等の額を1000万円にするには、有償減資1500万円しなければなりません。そう すると、資本金等の額1000万円(うち資本金500万円)、利益積立金500万円とな ります。
◆税の抵抗を受けない方法
しかし、資本剰余金の減少を直ちに資本金等の額の減少にする方法はあります 。自己株式の取得です。自己株式の取得は税法上は資本金等の額を減少する行為 とされているからです。
でも、「資本金+資本剰余金」が資本金等の額を超えていたら法人住民税均等 割の税率区分の基準は資本金等の額ではなく「資本金+資本剰余金」の額とする (平成27年以後)とされているので、自己株式の取得だけでなく、「資本金+資 本剰余金」と自己株式を相殺して消却処理をするというもう一つの手間が必要に なります。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-これに伴い、健康保険の認定対象者(被保険者の配偶者 を除く。)が19歳以上23歳未満である場合には扶養要件を年間収入150万円未満 することとなりました。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2025年7月の税務
◆ホスピスで高齢者が亡くなった場合の小規模宅地等の特例
◆資本金等の額減少で均等割節税
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆2025年7月の税務
-----------------------------------------------------------------------
7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1 月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
7月31日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定 める日)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆ホスピスで高齢者が亡くなった場合の小規模宅地等の特例
-----------------------------------------------------------------------
◆ホスピスとは
日本ホスピス緩和ケア協会の案内によると、ホスピスとは、がんなど難病で治 療が困難となった患者さんとその家族のために医師・看護スタッフがチームで緩 和ケアを実施する施設です。
1960年代にイギリスで発祥し、これまで医療が担っ てきた「検査・診断・治療・延命」ではなく、終末期医療の患者さんの痛みと不 安を和らげ、患者さんに寄り添い、本人と家族のQOL(クオリティ・オブ・ライ フ)向上を目的としています。
緩和ケアは在宅で受けることも可能ですが、高齢者の場合、近年は子供世帯の 負担の大きさから病院内の緩和ケア病棟や地域で医師と連携できる有料老人ホー ムなどがホスピスとして利用されています。
◆小規模宅地等の特例適用は条文等から判断
高齢者の方がホスピスで亡くなった場合、小規模宅地等の特例(特定居住用宅 地)の適用関係について、税法にはホスピスという用語は出てこないので、国税 庁の質疑応答事例や条文などから判断します。
病院で亡くなった場合、質疑応答事例では、病院の機能等から居宅で起居しな いのは一時的なものであり、入院後、居宅が他の用途に供されたような特段の事 情がない限り、生活の拠点は居宅にあり、小規模宅地等の特例の適用対象になる としています。
したがって緩和ケアで病院に入院していた場合も同様の扱いとな るものと思われます。
次に、有料老人ホームで緩和ケアを受けていた場合は、租税特別措置法第40条 の2第2項の要件に該当するかを確認します。
すなわち、被相続人が相続開始直 前において
(1)要介護または要支援状態にあること、かつ、
(2)老人福祉法第29条 第1項に定める施設であること、
そのうえで自宅の生活資材はそのまま、賃貸や 事業の用に供していないなどの要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用対象 になります。
また、特別養護老人ホームなど他の施設の場合でも、各法令で定め る施設に該当すれば、同様に小規模宅地等の特例の適用対象になります。
◆有料老人ホームの確認方法
有料老人ホームの事業者は、事業所の設置に際し、事前に都道府県知事に届出 が義務付けられ、公開されています。
また、契約に際して交付される重要事項説 明書の記載をもとに事業内容を確認することもできます。小規模宅地等の特例適 用について判断する際は、上記(1)(2)の要件を満たしているかをしっかり確認し ましょう。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆資本金等の額減少で均等割節税
-----------------------------------------------------------------------
◆法人住民税の均等割
法人道府県民税の均等割税は資本金等の額の5区分、法人市町村民税の均等割 税は資本金等の額の5区分と従業員の数の2区分とによって決められています。
所得の有無に関係なく、赤字でも負担しなければなりません。資本金等の額1000 万円以下、従業員数50人以下の分類区分が税負担の最少区分です。
◆減資で均等割節税への試み
ところで、この税負担の軽減を企図して資本金の減少手続きをする場合があり ます。
でも、資本金を減らしただけでは均等割税の軽減はできません。減資資本 金は資本剰余金の額に振り替わるだけで、資本金等の額の総額に影響しないから です。
資本金等の額は税法上の概念で、株式発行や組織再編で受け入れた出資額の内 、資本金とした金額とそれ以外の金額の合計とされており、会計上の「資本金+ 資本剰余金」に近い概念です。
◆資本金等の額の減少への税の抵抗
なお、資本金等の額を実際に減らそうとして有償減資や資本剰余金の配当をし たとしても、資本金等の額が直ちに減少するとは限りません。
税務的には、「資 本金等の額×資本剰余金減少額÷簿価純資産額=減少資本金等の額」の算式で計 算されることになっているからで、簿価純資産の中に利益剰余金がある限り資本 剰余金の減少を直ちに資本金等の額の減少にすることはできません。
例えば、資本金2000万円、資本剰余金0円 利益剰余金1000万円の会社が資本 金等の額を1000万円にするには、有償減資1500万円しなければなりません。そう すると、資本金等の額1000万円(うち資本金500万円)、利益積立金500万円とな ります。
◆税の抵抗を受けない方法
しかし、資本剰余金の減少を直ちに資本金等の額の減少にする方法はあります 。自己株式の取得です。自己株式の取得は税法上は資本金等の額を減少する行為 とされているからです。
でも、「資本金+資本剰余金」が資本金等の額を超えていたら法人住民税均等 割の税率区分の基準は資本金等の額ではなく「資本金+資本剰余金」の額とする (平成27年以後)とされているので、自己株式の取得だけでなく、「資本金+資 本剰余金」と自己株式を相殺して消却処理をするというもう一つの手間が必要に なります。