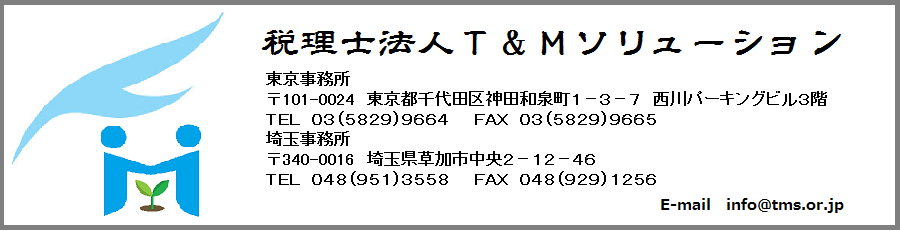
URL http://www.tms.or.jp
事務所だより 令和6年12月号
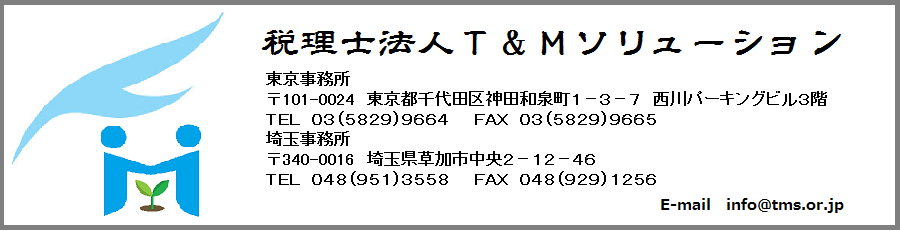
>最近のアメリカ大統領選と兵庫県知事選で大手メディアは民意とズレた「偏向報
道」を批判されています。
大手メディアは「権力の監視」を掲げ、政治家や有名 人という「権力者」に不正・不祥事があれば徹底的に糾弾します。その一方で実 は公務員、弁護士・医師・大学教授、他のメディアという「権威」に弱く、一方 の主張ばかりを取り上げる傾向があり、様々な意見が投稿されるYouTubu等のS NSより片寄りが指摘されます。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2024年12月の税務
◆申告書に収受印を押してくれない
◆労働基準法の代表的な帳簿とは
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆2024年12月の税務
-----------------------------------------------------------------------
12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収税額(6月〜11月分)の納付
翌年1月6日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除 申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で 定める日)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆申告書に収受印を押してくれない
-----------------------------------------------------------------------
◆令和7年1月以後は
国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申 請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務 署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。
申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通 知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォ ーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本( 提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。
◆申告書等提出事実を証明する方法
それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを 証明すればよいのでしょうか。
(1)Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で 交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、 希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答していま す。
(2)所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書 等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。
閲覧に手数料 はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コヒーの提供は受けられませ ん。
ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影 が可能となります。
(3)納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済 み申告書の内容を間接的に証明します。
(4)個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求の み)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります 。
◆銀行等は対応を変えないと
これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請 、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中 小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今 後は、どうなるのでしょうか。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆労働基準法の代表的な帳簿とは
-----------------------------------------------------------------------
>
◆労働関係帳簿は労働時間や賃金払いに必須
労働者を使用していると労働者名簿等の帳簿の作成や保存が必要です。
各種の 帳簿は労働時間管理や賃金支払い等には欠かせないもので、事業主には正しく作 成・運用することが求められています。
◆義務付けられている法定4帳簿
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇管理簿は法定4帳簿とも言われ ていて作成が必要です。
(1)労働者名簿(労基法107条)
労働者名簿は、本社や支店の各事業場において使用する労働者ごとに作成しま す。
労働者名簿には、氏名、生年月日、学歴や職歴、性別、住所、従事する業務、 雇入年月日、退職年月日と退職理由等の項目を記載します。
(2)賃金台帳(労基法第108条)
賃金台帳は雇用される労働者について作成します。
氏名、性別、賃金計算期間 、労働日数、時間外労働、深夜労働、休日労働の時間数、基本給、諸手当の種類 と金額、控除項目と金額等の項目を記載します。
(3)出勤簿
出勤簿は労基法上には明記されていません。「労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において労基法の109条の「その 他労働関係に関する重要な書類」に該当する書類とされています。
労働安全衛生 法(第66条8の3)でも出勤簿の作成と労働時間の把握をすることが事業主に課さ れています。
出勤簿には氏名、出勤日、出勤日の始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働時 間を記載します。
労基法で労働時間の規定が適用除外とされている管理監督者は 労働時間の記載は必要ありませんが、労働時間の把握は必要とされています。
(4)年次有給休暇管理簿
平成31年4月に実施された年5日の年次有給休暇取得義務化に伴い新たに作成義 務が課されました。氏名、付与日、付与日数、取得日などを記載します。
前述の4帳簿の保存期間は5年間とされていますが当面は3年間とされていま す。他に雇入れ、解雇、災害補償、賃金、労働関係重要書類も保存が義務付けら れ、デジタルデータによる保存も認められています。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-大手メディアは「権力の監視」を掲げ、政治家や有名 人という「権力者」に不正・不祥事があれば徹底的に糾弾します。その一方で実 は公務員、弁護士・医師・大学教授、他のメディアという「権威」に弱く、一方 の主張ばかりを取り上げる傾向があり、様々な意見が投稿されるYouTubu等のS NSより片寄りが指摘されます。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2024年12月の税務
◆申告書に収受印を押してくれない
◆労働基準法の代表的な帳簿とは
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆2024年12月の税務
-----------------------------------------------------------------------
12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収税額(6月〜11月分)の納付
翌年1月6日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除 申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で 定める日)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆申告書に収受印を押してくれない
-----------------------------------------------------------------------
◆令和7年1月以後は
国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申 請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務 署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。
申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通 知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォ ーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本( 提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。
◆申告書等提出事実を証明する方法
それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを 証明すればよいのでしょうか。
(1)Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で 交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、 希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答していま す。
(2)所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書 等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。
閲覧に手数料 はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コヒーの提供は受けられませ ん。
ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影 が可能となります。
(3)納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済 み申告書の内容を間接的に証明します。
(4)個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求の み)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります 。
◆銀行等は対応を変えないと
これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請 、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中 小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今 後は、どうなるのでしょうか。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆労働基準法の代表的な帳簿とは
-----------------------------------------------------------------------
>
◆労働関係帳簿は労働時間や賃金払いに必須
労働者を使用していると労働者名簿等の帳簿の作成や保存が必要です。
各種の 帳簿は労働時間管理や賃金支払い等には欠かせないもので、事業主には正しく作 成・運用することが求められています。
◆義務付けられている法定4帳簿
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇管理簿は法定4帳簿とも言われ ていて作成が必要です。
(1)労働者名簿(労基法107条)
労働者名簿は、本社や支店の各事業場において使用する労働者ごとに作成しま す。
労働者名簿には、氏名、生年月日、学歴や職歴、性別、住所、従事する業務、 雇入年月日、退職年月日と退職理由等の項目を記載します。
(2)賃金台帳(労基法第108条)
賃金台帳は雇用される労働者について作成します。
氏名、性別、賃金計算期間 、労働日数、時間外労働、深夜労働、休日労働の時間数、基本給、諸手当の種類 と金額、控除項目と金額等の項目を記載します。
(3)出勤簿
出勤簿は労基法上には明記されていません。「労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において労基法の109条の「その 他労働関係に関する重要な書類」に該当する書類とされています。
労働安全衛生 法(第66条8の3)でも出勤簿の作成と労働時間の把握をすることが事業主に課さ れています。
出勤簿には氏名、出勤日、出勤日の始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働時 間を記載します。
労基法で労働時間の規定が適用除外とされている管理監督者は 労働時間の記載は必要ありませんが、労働時間の把握は必要とされています。
(4)年次有給休暇管理簿
平成31年4月に実施された年5日の年次有給休暇取得義務化に伴い新たに作成義 務が課されました。氏名、付与日、付与日数、取得日などを記載します。
前述の4帳簿の保存期間は5年間とされていますが当面は3年間とされていま す。他に雇入れ、解雇、災害補償、賃金、労働関係重要書類も保存が義務付けら れ、デジタルデータによる保存も認められています。